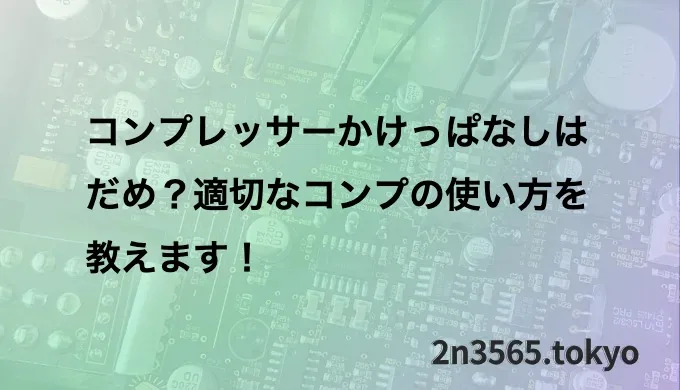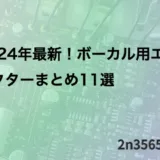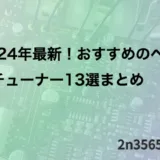ギターのコンプレッサーは「かけっぱなし」でOK?
「コンプレッサーって、かけっぱなしでいいの?」「音が潰れたりしない?」そんな疑問を抱えていませんか?コンプレッサーはギタリストの音作りを助ける強力なエフェクターですが、使い方を間違えると逆効果になることも。この記事では、コンプレッサーをかけっぱなしにするメリット・デメリットから、音が痩せない自然な設定のコツ、シーン別の使い方、おすすめモデルまで徹底的に解説します!この記事を読めば、あなたもコンプマスターになれるはずです!
そもそもコンプレッサーとは?音を整える魔法の箱
コンプレッサー(コンプ)とは、一言でいうと「音の粒を揃える」エフェクターです。小さな音を持ち上げ、大きすぎる音を抑えることで、全体の音量を均一に整えてくれます。これにより、クリーントーンでのアルペジオが綺麗に聞こえたり、ギターソロのサステイン(音の伸び)を稼いだりすることができます。
コンプの音作りを司る4つのツマミ
コンプレッサーには主に4つの基本的なツマミがあります。これらの役割を理解することが、効果的な音作りの第一歩です。
- スレッショルド (THRESHOLD):コンプが作動し始める音量の基準。「この音量を超えたら圧縮を開始!」というラインを決めるツマミです。
- レシオ (RATIO):音をどれくらいの比率で圧縮するかを決めます。例えば「4:1」なら、基準を超えた音量を1/4に圧縮します。
- アタック (ATTACK):音が出てからコンプがかかり始めるまでの速さ。速いとピッキングの瞬間から圧縮され、遅いとアタック感を残しやすくなります。
- リリース (RELEASE):音が基準値を下回ってから、コンプが解除されるまでの速さを調整します。
【結論】コンプかけっぱなしのメリット vs デメリット
コンプレッサーを常時ONにする「かけっぱなし」。多くのプロギタリストも実践していますが、もちろん良い面と悪い面があります。両方を理解して、自分に合った使い方を見つけましょう。
かけっぱなしのメリット
- 音量が安定し、演奏が上手く聞こえる:ピッキングの強弱による音量のムラがなくなり、特にカッティングやアルペジオで粒立ちの揃ったプロのようなサウンドになります。
- サステインが伸びる:音が長く持続するため、ギターソロやロングトーンがより滑らかに、表現力豊かになります。
- アタック感が強調される:設定次第で「パコッ」とした独特のアタック感が得られ、カッティングなどにグルーヴ感を加えることができます。
かけっぱなしのデメリット
- ダイナミクスが失われる:音の強弱が均一化されるため、ピッキングニュアンスによる表現力が乏しくなり、演奏が平坦に聞こえることがあります。
- 音が「つぶれる」ことがある:圧縮をかけすぎると、アタック感がなくなり、不自然で詰まったようなサウンドになる可能性があります。
- ノイズが目立ちやすくなる:小さな音を持ち上げる特性上、ギターやケーブルのノイズ、アンプのサーという音まで増幅してしまうことがあります。
失敗しない!コンプを「かけっぱなし」にする時の設定のコツ
では、デメリットを抑えつつ、メリットを最大限に活かすにはどうすればいいのでしょうか?かけっぱなしを成功させるための重要なポイントを3つ紹介します。
コツ①:バレない程度に「薄くかける」のが基本
かけっぱなしの極意は、「エフェクトがかかっているか分からない程度に薄く設定する」ことです。音を積極的に変化させるのではなく、あくまで「下地を整える」感覚で使いましょう。
- スレッショルド:高めに設定し、強く弾いた時にだけ軽くかかるようにする。
- レシオ:2:1 〜 4:1 程度の低めの設定にし、圧縮感を抑える。
コツ②:ON/OFF時の音量差をなくす
コンプをONにした途端に音が大きくなったり小さくなったりしないよう、アウトプット(レベル)のツマミで音量を調整しましょう。エフェクトをOFFにした時の音量と揃えるのが基本です。これにより、他のエフェクターとの組み合わせもスムーズになります。
コツ③:ブースターを併用してソロで音量を持ち上げる
コンプで音の粒を揃えると、ギターソロで音量を上げたい時に迫力が出にくいことがあります。そんな時はブースターを使いましょう。コンプで整えられたサウンドを、ブースターで純粋に持ち上げることで、音が埋もれず、前に出てくるソロサウンドを作れます。
接続順は「コンプレッサー → ブースター」がおすすめです。これにより、コンプで整えた音をクリーンにブーストできます。
どれを選ぶ?コンプレッサーの主要3タイプとおすすめモデル
コンプレッサーには、内部の回路によっていくつかの種類があり、それぞれサウンドのキャラクターが異なります。ここでは代表的な3つのタイプを紹介します。自分の出したい音に合ったモデルを見つけましょう!
① ROSS / MXR Dynacomp系 (OTA式)|パコッと気持ちいいサウンド
ギタリストに最も馴染み深いのがこのタイプ。「パコッ」と気持ちの良いアタック感が特徴で、カントリーのチキンピッキングやファンクのカッティングに最適です。シンプルな操作性のモデルが多く、初心者にもおすすめです。
代表モデル:Keeley Compressor Plus
定番のROSS系のサウンドを基に、より多機能に進化したペダル。アタックやトーンの調整が可能で、ナチュラルなサウンドから個性的なパコパコサウンドまで幅広く作れます。
② UREI 1176系 (FET式)|速くてパワフルなサウンド
伝説的なスタジオ機材「UREI 1176」のサウンドを元にしたタイプ。非常に速いアタックと力強い圧縮が特徴で、ロックやメタルのパワフルなギターサウンドに最適。音をグッと前に押し出したい場合におすすめです。
代表モデル:Origin Effects Cali76 Compact Deluxe
スタジオ品質のコンプレッションをペダルサイズで実現した最高峰モデル。非常にクリアでありながら、力強く音楽的なサウンドが得られます。
③ Teletronix LA-2A系 (オプティカル/フォトカプラ式)|自然で滑らかなサウンド
光(フォトカプラ)を使って音を圧縮するタイプ。動作が非常に滑らかで、「いかにもコンプをかけました」という感じがしない自然なサウンドが特徴です。アコースティックギターや、繊細なクリーントーンに最適です。
代表モデル:Diamond Compressor
オプティカルコンプの代表格。非常にナチュラルで温かみのあるサウンドが特徴で、かけっぱなしにして音にハリとツヤを与える使い方で絶大な人気を誇ります。
【シーン別】コンプレッサーの具体的な設定例
ここでは、特定の音楽スタイルに合わせた具体的なセッティング例を紹介します。まずはここから試してみてください!(※数値はあくまで目安です)
クリーンサウンドでのアルペジオ・カッティング
音の粒を揃え、煌びやかなサウンドを目指します。
- スレッショルド:やや低め(-20dB前後)
- レシオ:3:1 or 4:1
- アタック:速め(5ms前後)
- リリース:速め(50ms前後)
伸びやかなギターソロ
アタック感を残しつつ、サステインをしっかり稼ぐ設定です。
- スレッショルド:高め(-10dB前後)
- レシオ:3:1
- アタック:やや遅め(20ms前後)
- リリース:中程度(100ms前後)
歪みエフェクターと組み合わせる際は、コンプをかけすぎると音が潰れやすくなります。歪ませる場合は、コンプの設定をより薄めにするのがおすすめです。
Q&A:コンプレッサーに関するよくある質問
かけっぱなしにすると音痩せしませんか?
質の高いコンプレッサーを選び、「薄くかける」ことを意識すれば、音痩せはほとんど気になりません。音が細く感じたら、レシオを下げたり、トーン調整機能のあるモデルを使ったりして補正しましょう。
コンプレッサーはエフェクターボードのどこに繋ぐのが良いですか?
一般的には、ギターの直後、歪み系エフェクターの前に接続することが多いです。これにより、ノイズの増幅を抑えつつ、クリーンな信号を圧縮できます。ただし、歪みの後に繋いで音量を整える使い方もあり、ルールはありませんので色々試してみるのが一番です。
初心者におすすめのコンプレッサーは?
まずは、コントロールがシンプルな「MXR Dyna Comp」や、多機能で万能な「Keeley Compressor Plus」あたりから試してみるのがおすすめです。サウンドの方向性が分かりやすく、コンプの基本を学ぶのに最適です。
まとめ:コンプレッサーを味方につけて、音作りをレベルアップしよう!
コンプレッサーは、決して「分かりにくいエフェクター」ではありません。その役割と設定のコツさえ掴めば、あなたのギターサウンドを格段に向上させてくれる頼もしいパートナーになります。
今回のポイントをまとめます。
- 「かけっぱなし」はメリットが多いが、ダイナミクスが失われるデメリットもある。
- 成功の秘訣は「バレない程度に薄くかける」こと。
- 自分の出したい音に合わせて、コンプのタイプを選ぶのが重要。
- まずはこの記事の設定例を参考に、自分の機材で色々試してみよう!
コンプレッサーを正しく理解し、使いこなすことで、あなたの演奏はもっと楽しく、表現力豊かになるはずです。ぜひ、自分だけの設定を見つけてみてください!