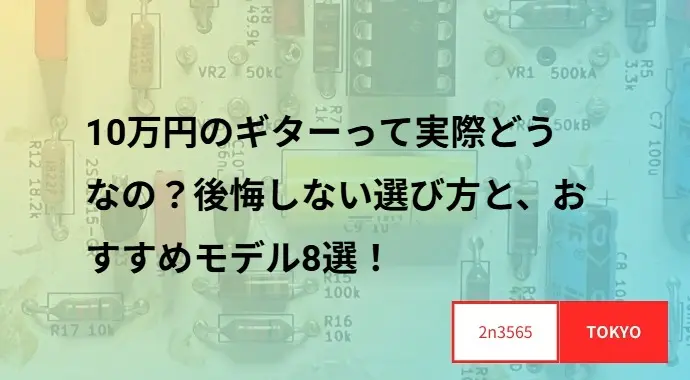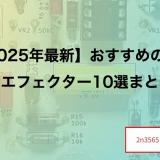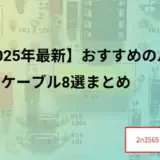最初の本格機を選ぶ時間は、ちょっとした旅です。手に取った瞬間のグリップ感、アンプに繋いだときの第一声、ステージでの取り回し、、、どれも外せません。私もはじめの一本を都内のスタジオで鳴らした日の鼓動をまだ覚えています。
結論はシンプル。10万円前後のエレキギターは、実用性と価格のバランスが抜群。量産技術の進歩で、フレット処理や塗装、電装の精度が底上げされています。ここでは、体験に根ざした視点で「後悔しない一本」を選ぶコツと、現場で頼れる推しモデルを紹介します。
10万円台と30万円台の違いはどこに出る?
木材と仕上げの精度
高価格帯は選別されたトーンウッドと、時間をかけた手作業の仕上げが強み。フレット端の処理や塗膜の均一さ、エッジの仕立てなど、触れた瞬間の“あたりの良さ”に差が出ます。とはいえ近年はこの価格帯でも丁寧な処理が一般的になりました。
ピックアップと電装の表現幅
高額機はダイナミクスの追従性や低ノイズで一歩先へ。ただ、ライブ現場ではPAを通すため、思ったほど差が出ない場面も多いです。自分のジャンルに合う構成を選ぶことのほうが効きます。
安定性と手放すときの価値
ネックの安定や中古相場は上位機に分がありますが、信頼ブランドの10万円前後でも日々のメンテを丁寧に行えば長く使えます。
まずは“改造の素体”として考えるのもアリ
この価格帯のエレキギターは、ピックアップやポット、ブリッジ、ペグなどを見直すと、上位クラスに迫る音や扱いやすさを引き出せる個体が少なくありません。20万円以上のモデルと比べても遜色ないところまで持っていける場合もあります。逆に重さや木材グレードは後から替えにくい要素。ここは購入時にしっかり見ましょう。
基本的に軽いエレキギターの方が体に負担が少なく、よく鳴る傾向があります。特に長時間練習やライブを考えると、軽さは重要なポイントです。代表的なタイプごとの目安は次の通りです。
| タイプ | 軽く感じる重さ | 平均的な重さ | 重く感じやすい重さ |
|---|---|---|---|
| ストラトキャスター | 3.0〜3.3kg | 約3.5kg | 3.6kg以上 |
| テレキャスター | 2.9〜3.2kg | 約3.4kg | 3.5kg以上 |
| レスポール | 3.8〜4.0kg | 約4.2kg | 4.5kg以上 |
| SG | 3.0〜3.3kg | 約3.5kg | 3.6kg以上 |
| ES-335タイプ | 3.2〜3.4kg | 約3.5kg | 3.8kg以上 |
木材の見方とピース数のチェック
シースルー塗装は継ぎ目(ピース数)が視認しやすいので、何枚接ぎか確認を。一般にピース数が少ないほど見た目・希少性の評価が上がりやすく、2〜3ピースなら十分合格。4ピース以上でも音が悪いとは限りませんが、中古の売却時はやや不利になりやすい傾向があります。レスポールのようにメイプルトップ+マホガニーバック構造なら、バック材の継ぎも見ておくと判断材料になります。塗りつぶし塗装でも、光の角度で継ぎ目がうっすら見えることがあります。
この価格帯はライブ・レコーディングで使える?
使えます。胸を張ってOKです。 弦高やオクターブ、ノイズ対策を詰めれば宅録でも十分通用。ライブでは手元のタッチと足元のペダルで抜けを作れます。大事なのは「セッティングの精度」と「現場での扱い方」。
失敗しない選び方チェック
初心者や2本目を考えている人が、店頭で確認しておきたいポイントをまとめました。
| チェック項目 | 見るポイント |
|---|---|
| ネックの握りやすさ | 手にしっかり馴染むか。高いフレットでチョーキングして引っかからないか。 |
| ピックアップの種類 | シングルは透明感、ハムは力強さ。ジャンルに合わせて選ぶ。 |
| ブリッジのタイプ | アームを使うならトレモロ付き、安定重視なら固定式。 |
| 重さとバランス | 立って弾いたときに肩や腰に負担が少ないか。 |
| 改造や交換のしやすさ | Fender系は交換パーツが豊富で長く使える。 |
【2025年版】10万円前後で推したいおすすめエレキギター
Fender Player II Stratocaster(約11万円)
Fender フェンダー エレキギター Player II Stratocaster® HSS, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst …
ブランドの成り立ちと位置づけ:1950年代からモダンミュージックの音を作ってきたFender。Player IIは現行の“標準機”として、扱いやすさと拡張性のバランスが優秀です。
主な愛用例(同系統アーティスト):ストラト系はジミ・ヘンドリックスやエリック・クラプトンらの代表例で知られ、クリーンの輝きとカッティングのキレが魅力。
主要スペックと注目点:モダンCネック、9.5インチ指板、5Way。ロールドエッジ指板で握りやすく、パーツ流通が豊富。改造の“素体”としても優秀。
Yamaha Revstar Standard RSS20(約9.5万〜10万円)
ブランドの成り立ちと位置づけ:設計の堅牢さに定評のある日本メーカー。Revstarはカフェレーサー文化に着想を得た独自路線で、チェンバード構造とカーボン補強ネックが長時間の演奏を支えます。
主な愛用例(ブランドとして):Yamahaのエレキは国内外の現場で長年支持。Revstarも海外レビューで高評価が多く、実戦投入例が増加中。
主要スペックと注目点:ハム×2、5Way、パッシブのフォーカススイッチでレンジ可変。取り回しの良い重量バランス。
Epiphone Les Paul Standard ’50s(約8万円前後)
ブランドの成り立ちと位置づけ:100年以上の歴史を持つ老舗で、現在はGibson直系。王道のセットネック+ハム構成で、力強いミッドとサステインを手頃に味わえます。
主な愛用例(ブランドとして):ジョー・ボナマッサをはじめ、Epiphoneのシグネチャー例も多数。クラシックなロック像に寄せたい人の定番入口。
主要スペックと注目点:太めのグリップ感、3Way、ハム×2。ミドル帯の“芯の太さ”が必要な編成で頼りになるタイプ。
Squier by Fender Classic Vibe ’60s Stratocaster(約7万円)
ブランドの成り立ちと位置づけ:Fender監修の姉妹ブランド。Classic Vibeは60年代の雰囲気を手頃に再現した人気シリーズで、初ステージ用にも安心感があります。
主な愛用例(同系統アーティスト):ストラト系はポップスからブルースまで守備範囲が広く、クリーンの粒立ちが持ち味。
主要スペックと注目点:アルニコ系PU、ヴィンテージルック。配線やPU交換を見越した拡張余地が豊富。
Ibanez RG421EX(約6万円)
ブランドの成り立ちと位置づけ:80年代以降の速弾き文化を牽引した日本ブランド。RGは代表的シリーズで、薄いWizard IIIネックとフラット指板が高速フレーズの弾きやすさに直結します。
主な愛用例(ブランドとして):スティーブ・ヴァイ、ポール・ギルバートなど超絶系の支持が厚い一方、モダンメタル〜フュージョンまで幅広く採用。
主要スペックと注目点:HH(Quantum)+5Wayでクリーンのカッティング域も確保。固定ブリッジは宅録でのピッチ安定が心強い。
Gretsch G5420T Electromatic(約11万〜13万円)
グレッチ GRETSCH G5420T Electromatic Classic Hollow Body Single-Cut with Bigsby ORG エレキギター
ブランドの成り立ちと位置づけ:1930年代創業。フルアコとBigsbyの組み合わせで、ロカビリー〜ブリットポップの象徴的トーンを作ってきた老舗です。
主な愛用例(ブランドとして):ブライアン・セッツァー、ジョージ・ハリスンなど。クリーンの煌めきと、軽い歪みでの空気感が独特。
主要スペックと注目点:メイプルラミネート胴、改良ブレイシング、Filter’Tron系PU。箱鳴りとフィードバック耐性のバランスが近年向上。
Sire Larry Carlton シリーズ(約10万円)
ブランドの成り立ちと位置づけ:新興ながら、触れた瞬間の仕上げ品質で台頭。ラリー・カールトン監修の設計思想で、実戦で使いやすい音域バランスにまとまっています。
主な愛用例(シリーズ):クリーン〜クランチで表情が付けやすく、歌ものやAOR的な文脈で扱いやすいキャラクター。
主要スペックと注目点:機種によりH-H/S-S-S/H-S-Sなど。ロールドエッジ指板や安定したフレットワークが価格帯以上。
PRS SE Custom 24(約15万円〜)
ブランドの成り立ちと位置づけ:1985年創業。上位機の思想を海外生産で最適化したSEは、“一本で幅広くこなす”現場で重宝されてきました。
主な愛用例(ブランドとして):カルロス・サンタナ、マーク・トレモンティなどメインストリームの採用例が豊富。
主要スペックと注目点:85/15 “S”系PU、コイルタップ、24F/25インチ。レンジが広く、コードもリードも破綻しにくい万能型。
中古を狙うなら――見落としがちなコストの話
中古は価格が魅力。ただしロッドの効き、フレットのすり合わせ〜ラウンド整形、ナットやサドルの調整まで「仕上げ直し」を要する個体は珍しくありません。結果として実戦投入できる状態に整えると新品以上の費用がかかることも。信頼できる店舗で状態を見極め、リペア予算をあらかじめ組み込むのが現実的です。
購入後にやっておきたいセットアップ
ナットの潤滑
黒鉛(鉛筆の芯)を溝に少量。チューニングの戻りが良くなり、アーム使用時も安定します。
ノイズの扱い
シングル搭載機はハーフトーンを覚えておくと静かなセクションで助かります。照明ノイズの強い箱では特に効果的。
プロ調整の活用
弦高・オクターブ・ネックの反り量を整えるだけで、別物の鳴りに。購入店やリペアに一度預ける価値は大きいです。
よくある質問
10万円前後のエレキギターでプロ現場に出ても問題ありませんか?
問題ありません。セッティングとノイズ管理を整えれば全国ツアーでも十分に通用します。
最初の一本として汎用性が高いのは?
Fenderの標準的モデルはカスタムの自由度が高く長く使えます。ロック寄りならレスポール系も選択肢です。
軽さはどれくらいを目安にすれば良い?
ストラトで3.0〜3.3kg、テレで2.9〜3.2kg、レスポールで3.8〜4.0kgあたりは軽めの感覚が出やすいです(体格や好みで個人差あり)。
中古のほうがお得ですか?
一見安いですが、ロッドやフレット処置などで整備費が上振れしやすいです。信頼できる店舗で状態と見積りを確認しましょう。
改造はどこから始めるのが定番?
まずはピックアップ。次にポット/配線、ブリッジ、ペグの順で効果とコストのバランスが取りやすいです。
まとめ
10万円前後のエレキギターは“練習用の域”を超えています。自分の手に合うネック、ジャンルに合うピックアップ構成、そして丁寧なセットアップ。この三つを押さえれば、長く付き合える相棒になります。
迷ったら、スタジオで少し大きめの音を。アンプから返ってくる第一声で、きっと決まります。