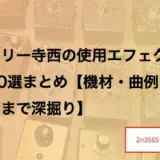どうも!エフェクターの自作歴は15年以上、ギター歴は18年。スタジオやライブ現場で「エフェクターに関するトラブル」を散々経験してきた立場から、2025年に本当に使いやすいループスイッチャー(=ループコントローラー)を厳選して紹介します!この記事は「ループスイッチャー エフェクター おすすめ」「ループスイッチャー エフェクター 使い方」で検索してきた方に向けて、仕組み・使い方・機種選びのコツまで一気通貫で解説!読み終わる頃には、あなたのボードに最適な一台が見えているはずです!
ループスイッチャーとは
ループスイッチャー(ループコントローラーとも呼ばれます)は、複数のペダルを「ループ」という単位にまとめ、ワンタッチで複数のエフェクトを同時にON/OFFしたり、モデルによっては接続順の並べ替えやパラレル接続、MIDI制御まで行える装置です。長いパッチケーブル配線による高域減衰やノイズの増加を抑えつつ、ライブでの複雑な踏み替えを一撃で実行できるのが最大のメリット!
呼び方は「ループスイッチャー」でも「ループコントローラー」でもOK。海外では“Loop Switcher/Loop Controller/Programmable Switcher”など複数の言い方があり、基本的には同義で使われています。
どんな使い方をするのか?
配線は「ギター → スイッチャーIN →(ループ1〜n)→ スイッチャーOUT → アンプ」が基本。モデルによってはインサートポイント(アンプのセンド/リターン)に入れて、歪み系はアンプ前、空間系はセンド/リターン側にまとめる構成も可能です!
- プリセット切替:クリーン用/バッキング用/ソロ用など、複数ペダルの組み合わせを一発呼び出し!
- バッファ管理:入力・出力のどちらに入れるか、ループごとに入れるかで高域ロスを最小化!
- MIDI連動:ディレイやリバーブ、アンプチャンネルをPC/CCで同時制御!
- 音作りの再現性UP:スタジオとライブで同じプリセットを再現しやすい!
電源容量が不足すると誤作動やノイズの原因になります。LCD搭載機やリレー駆動機は消費電流が大きめ。導入時はパワーサプライの余裕を必ずチェック!
2025年最新おすすめのループスイッチャー9選まとめ
One Control Agamidae Tail Loop(アガマダイ テイル ループ)
メーカーの説明
One Controlは2010年に日本でスタートしたブランド。コンパクトな筐体設計と実戦的なUI、そして国内生産に裏打ちされた信頼性で、プロからアマチュアまで幅広い支持を集めています。
製品の説明
必要十分な複数ループを手元で直感操作できるシンプル派の定番。音質を重視した配線で、原音の輪郭を保ちつつ複数ペダルの同時ON/OFFが可能です。どんな人が使っている?――ライブハウス規模の現場で「まずは踏み替えの手間を減らしたい」プレイヤー、サブボード構築や宅録用にミニマルな管理を求める人に選ばれる傾向があります。
BOSS MS-3 Multi Effects Switcher
メーカーの説明
1970年代からコンパクトペダルのスタンダードを築いてきたBOSS。堅牢な筐体、現場適応力の高いUI、長期供給とサポートの安心感で、「はじめての一台」からプロのワークホースまで幅広くカバーします。
製品の説明
3つの外部ループと内蔵マルチエフェクトを統合できるハイブリッド機。アンプのチャンネル切替や外部MIDI機器の制御も可能で、フライリグ(手荷物ボード)を組むときに無敵!どんな人が使っている?――全国ツアーやフェスで機材を最小化したいプロ、配信・宅録で「外部の推しペダル+マルチ」を同時運用したいクリエイターに人気です。
マルチエフェクトのモジュレーションやディレイは素晴らしいので、歪みやブースターをループにいれるのが良いでしょう。
HOTONE PATCH KOMMANDER LS-10
メーカーの説明
HOTONEはコンパクトに先鋭的な機能を詰め込む中国発ブランド。小型ながら視認性と操作性を両立する製品設計で、初・中級者のボード刷新にぴったりのラインナップを展開しています。
製品の説明
4チャンネルのプログラマブル・ループスイッチャー。小型ボードに収まりやすいサイズ感で、必要最低限のプリセット管理が行えます。どんな人が使っている?――初めてスイッチャーを導入する人、省スペースのミニボードで歪み・ブースター・モジュレーションなどを整理したい宅録勢に好まれます。
Moen GEC8JR
メーカーの説明
Moenはコストパフォーマンスに優れたペダルとスイッチャーで知られるブランド。堅実な筐体とわかりやすいUIで、予算重視のユーザー層に厚い支持があります。
製品の説明
8ループ+バンク/プリセット管理が可能なミドルクラスの定番。リレー切替のトゥルーバイパス設計で音痩せを抑え、横幅の割に配置がしやすいのが長所。どんな人が使っている?――スタジオ~ライブで「踏み替え一発」を実現したいロック/ポップス系のバンドギタリスト、費用対効果を重視するユーザーに選ばれます。
Musicom Lab MK-VI
メーカーの説明
Musicom Labは韓国発のスイッチャー専門ブランド。プロ現場からのフィードバックを反映したファーム更新や、細かなMIDI実装に強みがあります。
製品の説明
豊富なループ数、柔軟なインサート/ステレオ対応、緻密なMIDI実装で複雑なセットを一括制御できる上位モデル。クリックレス切替やプリセット構造が練られており、ツアーでの再現性が高いのもポイント。どんな人が使っている?――複数のデジタル空間系やアンプシミュレータをPC/CCで一括管理したいプロ、ギターテックがつく現場での堅牢な中核としての採用が目立ちます。
FREE THE TONE ARC-53M
メーカーの説明
FREE THE TONEは日本のプロビルダー出身チームによるブランド。精密な設計と高い音響思想、ケーブル/パッチ/ルーティングまで踏み込んだシステム構築力で、国内外のトッププレイヤーを支えています。
製品の説明
ARCシリーズは高品位バッファとクリックノイズを抑えたスイッチングが大きな魅力。53Mは実戦的なループ数とプリセット数を備え、日本製らしい静粛性と安定性を両立します。どんな人が使っている?――国内ポップス現場の精密なサウンドメイクを求めるセッション系、静音性と信頼性を重視するレコーディングエンジニア系ギタリストに選ばれる傾向があります。
One Control Crocodile Tail Loop OC10W
製品の説明
10ループ+2バッファのフラッグシップ級。ダイレクト/プログラム両モードに対応し、大量のドライブやモジュレーションを論理的に整理できます。どんな人が使っている?――多エフェクター派のフュージョン/プログレ系、ボードの見通しを良くしたい配信・解説系ギタリストに愛用者が多い印象です。
Electro-Harmonix Super Switcher
メーカーの説明
Electro-Harmonix(EHX)はNY発の老舗で、Big Muffなど伝説的なペダルを生み出してきた革新ブランド。独創性と実戦性を両立する製品群で世界のボードに欠かせない存在です。
製品の説明
大型筐体に視認性の高い表示、パッチ切替に合わせたタップテンポ、強力なMIDI連携を実装。広いフットプリントを活かし、つま先での誤操作を減らす物理配置も魅力。どんな人が使っている?――大編成バンドで曲ごとに音色変化が多いプレイヤー、照明が暗い現場でとにかく視認性を重視したい人に刺さります。
Carl Martin Octa-Switch MK3
メーカーの説明
デンマークのCarl Martinは、音響機器のノウハウを活かしたハンドメイド志向のブランド。堅牢な筐体とわかりやすい操作系で、ヨーロッパを中心に根強いファンを持ちます。
製品の説明
8ループをDIPスイッチで直感的に組み合わせる“メニュー不要”設計。マニュアルいらずで現場導入が速いのが美点です。どんな人が使っている?――MIDIは不要、でも一括切替は必要というブルース/カントリー系、機材トラブル時に現場で即座に把握したいシンプル派プロに好まれます。
昔はProvidenceやCustom Audio Japan(CAJ)のスイッチャーが国内の“定番”として多くのプロボードに入っていましたが、近年は流通が限られる/販売終了のモデルが増えた影響で、新規入手は難しくなりがちです。現在は本記事で挙げた各社の現行機が選択肢の中心になっています。
おすすめのループスイッチャーのまとめ
選ぶ基準は大きく5つ――ループ数、MIDI対応、ルーティング自由度(インサート/ステレオ/パラレル等)、サイズ/重量、価格帯です。
まずは手元のボードを書き出し、「いつ・どの場面で・何を一発で切り替えたいか」を明確にしましょう!
- ミニマル志向:HOTONE LS-10、One Control Agamidae(省スペース/直感操作)
- 多エフェクター派:OC10W、Moen GEC8JR(豊富なループと視認性)
- スタジオ~ツアーで再現性重視:Musicom Lab MK-VI、EHX Super Switcher(MIDI・表示機能が強力)
- 国産ハイファイ志向:FREE THE TONE ARC-53M(静粛性と作りの良さ)
- マルチ統合で機材圧縮:BOSS MS-3(外部ループ+内蔵エフェクト+制御を一台で!)
[p]最後に!導入後は電源容量・グラウンド配線・ケーブル品質の3点を見直すと、せっかくのスイッチャーが100%の性能を発揮します。スイッチャーは“音作りの脳”――設計段階からしっかり詰めれば、ライブでも宅録でも強力な武器になりますよ![/p]
よくある質問(FAQ)
ループスイッチャーとループコントローラー、何が違いますか?
呼び方の違いで、基本的には同じ機器を指します。海外でも複数の言い方があり、機能面の定義差はほぼありません。
MS-3のような「マルチ内蔵+ループ」は何が便利?
内蔵エフェクトでコーラスやディレイなどをまかないつつ、こだわりの歪みなどは外部ループに配置できます。機材点数と重量を減らしつつ、プリセットで一括管理できるのが最大の利点です。
ステレオ対応やパラレルルーティングは必要?
空間系を2台並列で使う、アンプ2台に振り分ける、IRローダーやラック機器を併用するなどの構成では有用です。今後の拡張予定があるなら、対応機を選んでおくと後悔しません。
音痩せが心配です。対策はありますか?
良質なバッファ(入力/出力)を適所に使い、ケーブル長を最小化すればOK。トゥルーバイパス至上主義ではなく、バッファ込みで「最終的に良い音」になる設計を目指しましょう。
さあ、あなたのボードに合う一台を選んで踏み替えストレスとサヨナラしましょう!「音作りの再現性」と「演奏への集中力」が一段上がるのを、きっと実感できるはずです!
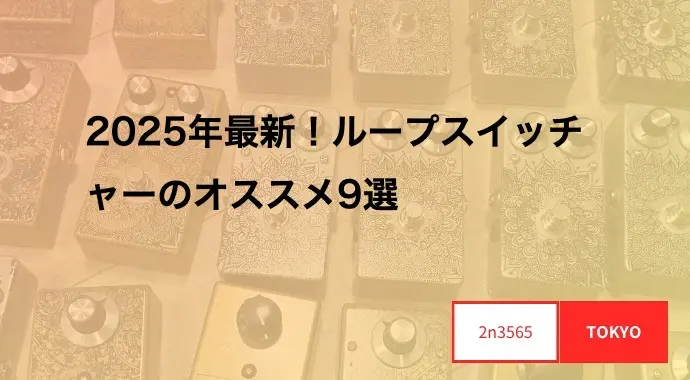



![HOTONE PATCH KOMMANDER LS-10 4チャンネル・プログラマブル・ループ・スイッチャー[国内正規品]](https://m.media-amazon.com/images/I/31te84GFVoL._SL500_.jpg)

![Musicom.Lab/EFX MK-VI [ループ・スイッチャー MIDI コントローラー]](https://m.media-amazon.com/images/I/31U8PYCZYCL._SL500_.jpg)